「通いの場」の立ち上げ、拡大、多様化、フレイル予防の観点を踏まえた「通いの場」の機能強化について学び、具体的に地域づくりにつながる介護予防活動を進めることができる核となる人材を育成します。
以下のマークは、各研修の開催方法になります。
なお、以下に記載の研修スケジュールは令和7年度のものになります。
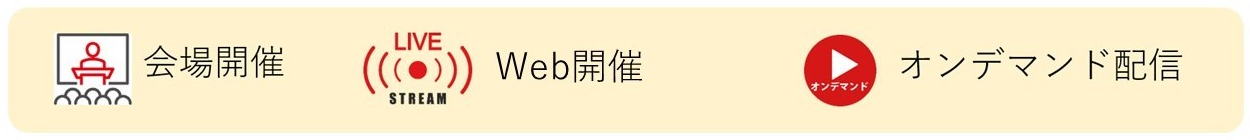
総論編(共通 ・ 一般介護予防 ・ サービス活動)![]()
【対象者】
〇一般介護予防事業
今年度の介護予防事業に携わる者を幅広く対象とします。
※管理職・担当者、新任・継続を問いません。関係機関や専門職を含みます。
〇サービス・活動事業
今年度の総合事業に携わる者を幅広く対象とします。
※管理職・担当者、新任・継続を問いません。関係機関や専門職を含みます。
【概要】
〇一般介護予防事業
総合事業全般の理念と意義、介護予防・フレイル予防の概論及び、各論(通いの場、運動器、口腔・栄養、社会参加、認知機能、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施)、短期予防集中サービスについて、研究成果を踏まえた根拠に基づく解説やセンター事業の紹介等を行う。
〇サービス ・ 活動事業
総合事業の目指すところと概要及び、自立支援・介護予防のための個別支援、自立支援・介護予防のための地域づくりに関する内容とする。
【目的】
〇一般介護予防事業
総合事業の理念と意義について理解するとともに、介護予防事業を実施するにあたり必要な、介護予防・フレイル予防の基礎知識及び通いの場づくりの重要性について理解を深めます。
〇サービス ・ 活動事業
全ての職種が総合事業(サービス・活動事業及び一般介護予防事業 )に関する基礎知識を学び、総合事業全体の理念や早期発見、早期介入の重要性を理解するとともに、各事業の意義について学ぶことを目的とします。
【年間計画(予定)】全2期、オンデマンド250名程度
※第1期、 第2期は同じ内容です。
【研修内容】
〇共通
•介護予防・フレイル予防概論
•自立支援の基本
•総合事業の理念・各サービスの意義と好事例
•医療的視点からみたフレイル予防
•高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施における通いの場の活用
〇一般介護予防事業
•通いの場について
•介護予防・フレイル予防各論(運動器・社会参加・口腔・栄養・認知機能)
〇サービス・活動事業
•自立支援・介護予防のための個別支援
•自立支援・介護予防のための地域づくり
通いの場実践編 タイプⅢ (運動系 )
【対象者】
介護予防事業担当の初任者または経験年数が少ない方で、心身機能の維持・向上を主な目的とした通いの場について理解を深めたい自治体、地域包括支援センター、社会福祉協議会職員、リハビリテーション専門職、東京都介護予防・フレイル予防推進員等を対象とします。
※通いの場実践編の研修参加は、総論編の研修参加が前提となります。昨年度までに総論編を受講されていない方は、今年度の総論編の受講をご検討ください。
【目的】
特に心身機能の維持・向上を主な目的とした住民主体の介護予防活動を地域に展開し、継続的な支援を行うために必要な手法を習得します。
【年間計画(予定)】全4回 定員40名程度
※第4回は、 実践編タイプⅠ ・ Ⅱ (多様性) と合同開催
【研修内容】
全4回の連続研修となります。
[第1回]
テーマ 「通いの場とは?~地域を把握する~」
•通いの場について
•前年度受講者の発表
•地域の把握
•担い手の特性
[第2回]
テーマ 「通いの場の計画作成とちょい足しプログラム 」
•通いの場の立ち上げ
•グループワーク~通いの場の立ち上げ手法~
•継続支援~機能強化支援・ちょい足し~
[第3回]
テーマ 「通いの場の評価と継続支援」
•グループワーク~ワークシートの共有~
•通いの場の評価
•グループワーク~評価設計~
•通所 C との連動
[第4回]
テーマ 「取組の進捗と成果報告」
•受講者発表
•総括
通いの場実践編 タイプⅠ ・ Ⅱ (多様性)
【対象者】
通いの場の立ち上げや支援を経験している者の中で、さらに多様な通いの場について理解を深めたい自治体、地域包括支援センター、社会福祉協議会職員、リハビリテーション専門職等を対象とします。
※令和 6 年度までに実践編Ⅰを受講している方、または令和7年度の実践編(運動系)を受講している方。
※通いの場実践編の研修参加は、総論編の研修参加が前提となります。昨年度までに総論編を受講されていない方は、今年度の総論編の受講をご検討ください。
【目的】
特に生きがい・楽しみや交流(孤立予防)を主な目的とした通いの場を、多様な主体と連携しながら地域に展開し、継続的な支援を行うために必要な手法を習得します。
【年間計画(予定)】全4回 定員40名程度
※第4回は、実践編タイプⅢ(運動系)と合同開催
【研修内容】※参加希望の回ごとに受講可能です。
全 4 回の連続研修となります。
[第1回]
テーマ 「多様な通いの場~地域を把握する~」
•多様な通いの場の立ち上げについて
•前年度受講者の発表
•通いの場の PDCA
•担い手の発掘と育成
[第2回]
テーマ 「多様な通いの場~民間連携・多世代の実践~」
•通いの場の立ち上げ手法
•民間連携
•多世代・多文化共生
[第3回]
テーマ 「多様な通いの場~継続支援~」
•多様な通いの場の評価
•グループの発展に沿った支援
•ちょい足し・多様なプログラム
[第4回]
テーマ 「取組の進捗と成果報告」
•受講者発表
•総括
通いの場 スキルアップ研修
【対象者】
通いの場実践編(運動系)および通いの場実践編(多様性)を受講の参加者は、適宜視聴可能とします。その他、区市町村において介護予防事業を担当する職員(地域 包括支援センター職員等を含む。)、東京都介護予防・フレイル予防推進員、生活支援コーディネーター、区市町村の介護予防事業に関わる専門職等(平成29年度~令和6年度の研修参加者、または今年度総論編を受講した者が望ましい。)
【目的】
フレイル予防の視点を踏まえた通いの場の立ち上げや評価指標、広報戦略などの支援手法を習得します。
【年間計画(予定)】全 6 回 各100名程度
※連続研修ではございません。
参加希望の回ごとに受講可能です。
オンデマンド配信 : 6月23日 (月) ~ 12月31日 (水)
【研修内容】
[第1回]
テーマ 「通いの場の広報 (チラシづくり )」
•情報発信の考え方の基礎
•チラシづくりの具体的手法
[第2回]※通いの場実践編受講者は必須
テーマ 「地域の把握」
•地域アセスメントの手法
[第3回]※通いの場実践編受講者は必須
テーマ 「通いの場の評価①」
•評価の意義・目的
•評価の種類と視点、評価指標の具体例
[第4回]※通いの場実践編受講者は必須
テーマ 「通いの場の評価②」
•評価の手法、結果の活かし方
[第5回]
テーマ 「プレゼンテーション資料の作り方 」
•全体構成の考え方とポイント
•伝わるスライド作成のポイント
[第 6 回]
テーマ 「プレゼンテーションの方法」
•プレゼンテーションの心構え、準備
•プレゼンテーションの実践例
【対象者】
自治体職員、東京都介護予防・フレイル予防推進員、第1層 生活支援コーディネーター等の庁内全体、もしくは各圏域で戦略を立案すべき者を対象とします。
※介護予防事業に携わり、地域資源の把握や通いの場づくりを中心とした行動計画 ・ 評価等を実施する方を幅広く対象とします。
※効果的・効率的に業務を推進していただくため、継続的な業務改善および理解の強化等を目的としており、令和2~6年度に受講された方も対象としております。 継続的な受講を推奨しています。
【目的】
東京都介護予防・フレイル予防推進員等が、通いの場を中心テ ーマに置き、事業開始前の地域診断から事業終了時の評価設計までの一連のPDCAサイクルを学び、一般介護予防事業の戦略的アプローチを習得する。
【年間計画 】 全5回、定員40名程度
【研修内容】
※全 5 回の連続研修となります。
[第 1 回]
テーマ 「地域づくり・地域診断」
•介護予防の取組 • 概論
•PDCA SMART 活用実践例
•地域資源の把握
•目的の階層化 • 戦略シート
[第 2 回]
テーマ 「庁内外連携」
•自治体の計画と情報共有
•関係機関との連携の実践例・ディスカッション
•多様な主体
[第 3 回]
テーマ 「PDCA サイクル」
•グループワーク : ロジックモデル
•担い手
•グループワーク : 実行シートの作成
[第 4 回]
テーマ 「評価 • 効果分析」
•評価~通いの場のレベル&事業 • 行政レベル~
•グループワーク : 評価
[第 5 回]
テーマ 「取組の進捗と成果報告」
•受講者発表
•総括
【対象者】
区市町村において介護予防事業を担当する職員 (地域包括支援センター職員等を含む)、生活支援コーディネーター(SC)、リハビリテーション専門職・短期集中予防サービス受託事業者※一般介護予防事業の実践編受講者には、職種に応じて当研修の受講を勧奨します。
【目的】
サービス・活動事業について、各職種に必要な専門知識やスキルを習得する。
【年間計画(予定)】
※連続研修ではございません。参加希望の回ごとに受講可能です 。
【研修内容】
[第 1 回] 行政職員対象
テーマ 「介護予防ケアマネジメントの啓発」
①介護予防ケアマネジメントの専門職への啓発
②自立支援に関する住民への啓発
[第 2 回] 地域包括支援センター職員対象
テーマ「介護予防ケアマネジメント」
①介護予防ケアマネジメントの考え方
②セルフマネジメント支援
[第 3 回] 生活支援コーディネーター対象
テーマ 「総合事業における生活支援コーディネーターの役割」
①総合事業における SC の役割を学ぶ
②個別事例と地域資源のマッチングと資源創出
[第 4 回] リハビリテーション専門職・短期集中予防サービス受託事業者対象
テーマ 「短期集中予防サービス」
①短期集中予防サービス等での目標設定
②セルフマネジメント支援(コーチングなど)手法
【対象者】
総合事業担当の行政職員係長級を中心として、関連する中心的な包括職員、生活支援コーディネーター等を含めたチームで参加します。
【目的】
各自治体のおける総合事業の構築・再編をするために、庁内関連部署にて、目指す高齢者の生活像や地域課題を共通認識し、課題解決に向けた体制やサービス内容の計画を策定し、実践する。
【年間計画(予定)】 全4回、各40名程度
【研修内容】
[第 1 回]
テーマ 「地域課題の把握と各事業で解決できる課題の検討」
目指す高齢者の生活像(ビジョン)を確認し、事前に実施したアセスメントをもとに、各自治体内の課題の整理と優先的に解決すべき課題を検討する。
[第 2 回]
テーマ 「課題解決の体系デザイン①(内部の体制、サービス提供)」
地域支援事業の体系デザイン、介護予防フローの設定をする。
[第 3 回]
テーマ 「課題解決の体系デザイン②(内部の体制、サービス提供)」
地域支援事業の体系デザイン、介護予防フローの設定をする。
[第 4 回]
テーマ 「短期集中予防サービスの構築・再編」
対象者像の整理とリクルート、プログラムの再考、評価指標の設定、終了後に活用できる資源を把握する。